企業を成長させるために積極的なM&Aを進めるタイプの経営者がいます。
そして投資家は意外と…こういう企業買収を繰り返す会社の株が好きなんですよね。
しかし私個人としては、
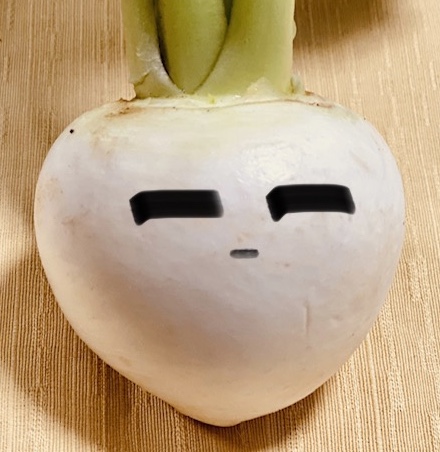
M&Aを成長の軸としている会社の株は要注意だと思っています
この記事では「なぜM&Aを繰り返す会社が注意なのか」と、「企業が行ったM&Aを個人投資がどう評価すべきか」という2点について書いてます。
また私はただの投資家であり、企業買収の専門家ではありません。
そのため、あくまでも個人投資家的な視点からの内容となっています。
目次
M&Aを成長のベースにする会社には要注意
この記事で取り上げている「M&Aを繰り返している企業」というのは実在し、時にその株価がビックリするくらいの高値になるケースもあります。
どうしてこんな事が起こるのかを、まず考えてみましょう。
株価が上がる理由はおそらくとてもシンプルで、
期待値がめちゃ高くなるから。
実際にM&Aってうまくいくと、急激に企業を成長させることがありますからね。
また成長が止まった会社を第二の成長ターンへ移行させるケースもあるでしょう。
ただ…個人的にはM&Aに期待して株を買うのには消極的です。
理由はこれまた単純で、
企業買収は失敗するケースが多いからです
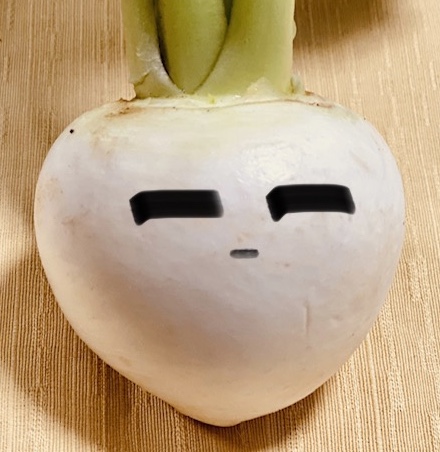
これは私のサラリーマンとしての経験からもきています。
実はわたし…平サラリーマンだった時に、働いていた会社が買収された経験があるんですよね。
私が学校を卒業して社会人となり、最初に入社した会社は、入社して2年目くらいの時に企業買収をされました。
その時の社内の混乱はひどく、私が「この人は優秀で仕事ができるな」って感じていた人の多くが退職をしてしまったのです。
さらに部長には親会社の人が座り、旧部長は副部長に、旧副部長は部長補佐という役職ができてそのポストにつきました。
ですが、そもそも…副部長は部長を補佐するのが役目ですよね?
なのに…追加で部長補佐って…「いったい何をする人なの!?」なんて思ったものです。
もちろん私がいた部署にも親会社の人が来たのですが、なんというか…文化が違いすぎて慣れるのに苦労しました。
そんな文化の違いが嫌で買収後に辞めてしまった人も多数います。
まあこんな感じで買収される側の会社も、なかなかに荒れるのです。
そのためM&Aをした会社というのは、買収された後に以前と同じ状況とは限りません。
つまり買収前と同じ収益をあげられるかは未知数ってことです。
だから企業買収を成功させるというのはハードルが高く、それはM&Aに期待して株を買うことの難易度が高いことも表しています。
さて続きまして、私が投資家としてM&Aされる会社を実際に評価するときに、注意している点を二つほど書いていきます。
収益性の低い企業のM&Aは要注意
M&Aのパターンとして、業績の悪い会社を買収し、立て直して利益をあげようとするケースが見受けられます。
でも、これ…とてもリスキーです。
先ほども書きましたが買収される側の企業は荒れることが多いので、以前と同じ収益をあげることさえ簡単ではありません。
そんな現状維持でさえ困難な中で、業績の悪い会社を立て直すなんてハードモードすぎるのです。
なぜかM&Aをする経営者の多くは、自分なら買収先の会社を立て直して、利益を増やせると考えるようなのですが…投資家として私がみている範囲でも成功するケースは少ないと感じます。
またこの業績の悪い会社を買収して立て直そうとするケースは、現在の業績が良い企業の経営者が行う傾向がみられます。
やっぱり自社の状況が良いとイケイケになるのかもしれません。
しかし実際には、畑違いの会社を買収して立て直せるようなスペシャルな経営者はごくごく一部だけなのが現実です。
つまり業績の悪い会社を買収して立て直すなんてのは「夢の話」だと考えましょう。
だから、
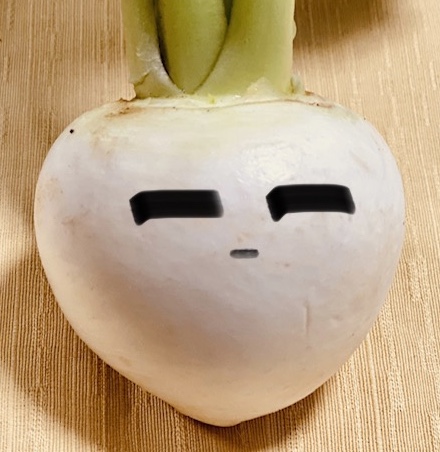
買収先の企業の収益性が高いかどうかは重要な要素です
もともとの収益性が高い会社ならば、買収後に少々落ち込んだとしても利益をだせますからね。
買収先企業と本業の間にシナジーがあるか
ついで重要なのは、本業と買収先企業のシナジー効果です。
シナジー効果とは相乗効果のことです。
ここでは買収先企業がグループに増えることで本業へのプラス効果があるのかや、本業を活用して買収された企業が成長できるのかって事です
たとえば買収した企業の商品を、本業の販売網を通して売る。
なんてのは分かりやすいシナジーですよね。
買収された側は営業マンを増やさなくても自社商品の売上を増やせます。
また本業が進出していない地域の同業者を買収なんてのもよくあるケースだと思います。
これにより未開拓エリアの販売網と顧客を一気に獲得です。
個人的には本業と同業種の買収ってのは、うまく行くケースが多いイメージですね。
やはり業種が似ていると買収後の影響が小さくてすみ、仕入れなど多くの面で効率化がしやすいのかもしれません。
買収される側もスケールメリットを得られますしね。
こんな風なシナジーがあると買収後に収益性が上昇する可能性があり、投資家としては美味しい訳です。
以上の2点が私が株主として企業買収を評価するポイントです。
細かい事を言えば他にもたくさんあるのですが、まずこの2点がもっとも重要だと思うので記載しました。